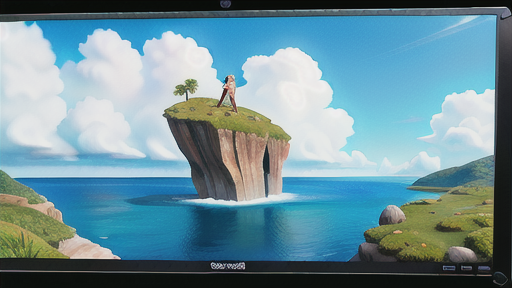映像用語辞典「ハ」– tag –
-

「場見る」〜舞台上の位置を決める用語〜
「場見る」とは、舞台上で各人が立つ位置を決める用語です。俳優やダンサーが、自分の動線を妨げないように、他の演者との関係性を考慮しながら、舞台上の適切な場所を確保することを指します。舞台の進行をスムーズに行い、観客に混乱のない演出を行うために不可欠な作業です。 -

映画・動画用語「鼻マイク」とは?
-鼻マイクとは?- 鼻マイクとは、鼻腔に装着する小さなマイクのことです。鼻腔内の振動を電気信号に変換し、音声を捉えます。従来のマイクとは異なり、口を覆わずに使用できるため、演技やダンス、スポーツなどのパフォーマンス中に音声の収録が可能です。 -

番組平均視聴率とは?
番組平均視聴率の定義とは、テレビ番組が放送された時間帯における視聴率の平均値のことです。視聴率は、番組を視聴している世帯の割合を表します。番組平均視聴率は、番組の全体的な人気や影響力を測る重要な指標です。視聴率調査会社によって測定され、主にテレビ局や広告代理店が番組の評価や広告費の決定に利用されています。番組平均視聴率が高ければ、その番組はより多くの人に視聴されており、広告効果が高まる可能性があります。 -

番組終了時視聴率とは?用語の意味と測定方法
-番組終了時視聴率の定義- 番組終了時視聴率とは、番組の最終放送時間にその番組を視聴していた視聴者の割合を表します。つまり、番組のエンディングの時点における視聴率のことです。放送の最初から最後まで視聴する視聴者だけでなく、途中でチャンネルを変えて番組の結末だけ見た視聴者も含まれます。 -

映画と動画の用語「番審」とは?
-番審とは- 番審とは、映画や動画の分野で使用される用語で、作品の出来栄えを評価して順位付けするシステムのことです。通常、批評家や審査員などの専門家が、事前に決められた基準に基づいて作品を審査し、優秀な作品に順位を付けます。番審は、映画祭やコンテストなどのイベントで広く利用されており、受賞作品やランクイン作品を決定するために使用されます。このシステムは、作品の水準やクリエイティブさを客観的に評価し、優秀な作品を表彰することを目的としています。 -

映画・動画撮影用語「番手」とは?
映画や動画撮影の世界でよく使われる用語に「番手」があります。これは、レンズや絞りの開口部のサイズを表す単位です。レンズの「F値」や絞りの「Fナンバー」とも呼ばれます。番手は、レンズを通過する光の量と、写真や動画の被写界深度に影響します。 -

番記者とは?映画と動画における意味を徹底解説
-番記者の定義と役割- 番記者とは、特定の対象(企業、組織、人物など)を継続的に取材し、ニュースや記事などを執筆するジャーナリストのことを指します。彼らの役割は多岐にわたり、対象の動向やニュース価値のある情報を把握し、それを正確かつ迅速に報道することです。さらに、番記者は対象との信頼関係を築き、独占的な情報を入手したり、重要な問題について洞察力を提供したりすることも期待されています。また、ソーシャルメディアやオンラインプラットフォームを活用して情報を配信し、読者との関わりを図ることも重要な役割です。 -

搬入とは?映画や動画制作における重要な工程を解説
搬入とは、映画や動画制作において、撮影に使用する機材や素材を撮影現場に搬入する重要な工程を指します。機材にはカメラ、照明、録音機器などが含まれ、素材には衣装、小道具、背景などのさまざまなアイテムが含まれます。搬入は、撮影を円滑に開始するための重要なプロセスであり、時間通りかつ効率的に実施する必要があります。 -

「反時計」映画や動画における左回転の秘密
映画や動画において、「反時計」とは、時計回りに回転するのではなく、反時計回りに回転することを指します。この現象は、映像の向きが上下または左右反転することによって発生します。時計回りの回転が「時計回り」であるのに対し、反時計回りの回転は「反時計回り」と呼ばれます。映像制作の分野では、反時計は意図的に用いられることがあり、特定の効果を生み出したり、ストーリーを伝えたりするために使用されます。 -

反響版の仕組みと役割を徹底解説
反響版とは、シネマや会議室などの音響効果を向上させるために使用されるデバイスです。反射する表面を持ち、音源から発せられた音を特定の方向やエリアに反射させる機能があります。これにより、音が均等に分散され、特定の周波数帯域を強調したり、残響時間を制御したりすることができます。反響版は、音の鮮明度と明瞭度を向上させ、聞き取りやすさを向上させるために不可欠なツールです。 -

半枠とは何?映画や動画で見かける用語の解説
半枠とは、映画や動画の配信において、通常の長編映画よりも短い「中編」または「短編」のコンテンツを指す用語です。その長さはおよそ15分から30分程度であり、1本の長編映画を2つに分割した「ハーフ」という意味で「半枠」と呼ばれます。 半枠の歴史は古く、19世紀後半の「nickelodeon」と呼ばれる映画館で上映されていました。当時、nickelodeonでは1本の長編映画を複数の「リール」に分けて上映していましたが、1リールは15分程度の時間で、これらは「半枠」と呼ばれていました。 -

舞台用語『半丸』とは?
-半丸とは?- 半丸とは、歌舞伎や日本舞踊など舞台芸術で用いられる特殊効果です。舞台上の中央に、半円形の板状の形をしたものを配置し、演者がこの上に立つことで、まるで空中を歩いているかのような演出を行います。 半丸の中央部は、演者が立つ部分として切り抜かれており、演者は半丸の下側を足で踏んで支えます。半丸は、傾斜をつけることで、角度をつけることができ、よりダイナミックな動きを表現することが可能です。 -

発局を徹底解説!知っておきたい映画と動画用語
発局の定義と役割 発局とは、映画や動画の冒頭で流れる短いシーンのことであり、作品のテーマや雰囲気を観客に伝える重要な役割を持っています。発局は、視聴者にストーリーの背景や設定を提供し、登場人物の動機や性格に関するヒントを与えます。また、作品のトーンを設定し、観客の期待や好奇心を喚起します。発局は、作品の全体的な印象を決定づけ、観客を引き込むための重要な要素となるのです。 -

映画と動画の用語『発々』について
映画や動画業界では、「発々」という用語が使用されています。これは、撮影した映像の不要な部分を除去する作業を指します。映像制作では、撮影した映像には余分な部分や不要な要素が含まれていることが多く、これらの部分をカットすることで、動画をより簡潔で魅力的にすることができます。 -

映画や動画における箱書きとは?
-箱書きとは?- 箱書きとは、映画や動画のタイトルの下に表示される短い説明文のことです。 ジャンル、要約、キャッチーなフレーズなど、視聴者に作品の内容を簡潔かつ魅力的に伝える役割があります。箱書きは、視聴者を引きつけ、作品に関心を持たせる重要な要素です。 この説明文は、視聴者が作品を選択する際に重要な情報源となります。適切な箱書きは、視聴者の期待値を設定し、内容が自分たちの興味に合致しているかどうかを判断するのに役立ちます。また、ソーシャルメディアや検索エンジンでの作品の宣伝にも重要な役割を果たします。 -

薄暮の美しさを捉える:映画や動画における『薄暮』の用語
薄暮とは、日没前後における短い期間で、太陽が地平線近くに沈んで空が美しい色合いに染まる時間帯を指します。このシネマジックな瞬間は、映画や動画の中で、情緒的なムードや劇的な効果を演出するために巧みに用いられてきました。 映像表現では、薄暮は通常、暖かく柔らかい光で特徴付けられます。オレンジ色や紫色のニュアンスが混ざり合い、空や被写体にドラマチックな輝きを与えます。映画監督は、この独特な光を利用して、ノスタルジーや物思いに耽る感情を喚起したり、臨場感のある没入的な雰囲気を生み出したりします。 -

拍手取りとは?映画や動画の用語を解説
拍手取りとは、映画や動画において、観客が拍手で作品の一部を強調したり喝采を送ったりする行為を指します。観客が拍手によって、作品内の特定のシーンや俳優のパフォーマンス、あるいは映画全体に対する賞賛を表現します。拍手取りは、観客の熱狂や親しみを表し、ひいては作品の人気や評判を高めることに貢献します。 -

映画の配給収入とは? 興行収入との違いを解説
映画の配給収入とは、映画の配給会社が興行収入から得ている収益のことです。配給会社は、映画館に映画を上映する権利を映画制作会社から買い取ります。その後、映画館に映画を上映させることで得られる収入の一部を受け取ります。配給収入は、映画の制作費や宣伝費などの経費を賄うのに使われます。 -

映画と動画用語『背景』の基礎知識
映画や動画における「背景」とは、画面に映し出される人物や物体の周囲を構成する視覚的な要素を指します。風景、建物、インテリア、小道具などを含み、シーンの雰囲気や状況を伝える重要な役割を担います。背景は、物語の設定、登場人物の性格、プロットの展開に関連付けられて使用されます。つまり、背景は単なる視覚的な装飾ではなく、作品のテーマやメッセージを伝える重要な要素として機能するのです。 -

映画と動画の用語『外す』の意味とは?
映画や動画撮影において、「外す」とは、狙った被写体をうまく捉えられないという意味です。被写体が動いていたり、カメラの設定が適切でなかったり、手ブレやピントのずれなどにより、被写体がぼやけたり、フレームアウトしたりしてしまうことがあります。この場合、被写体を撮り損ねてしまい、「外した」と表現されます。 -

映像用語『ぱかつき』を徹底解説
映像用語の「ぱかつき」とは、映像の明暗が激しく変化する現象のことです。原因としては、照明のちらつきやカメラのシャッター速度との不一致などが挙げられます。ぱかつきは、視聴者に不快感を与えたり、映像の質を低下させたりする可能性があります。そのため、映像制作においては、ぱかつきの発生を抑えることが重要です。 -

映画・動画の現場用語『ばらめし』とは?
映画や動画の現場で、昼食のことを「ばらめし」と呼びます。ばらめしが何を指すかというと、ご飯と総菜を容器に入れて配られる弁当のことです。この言葉の由来は諸説ありますが、炊き立てのご飯に総菜をのせる様子が、花弁を散らしたバラに似ているという説が有力です。 -

映画・動画用語『ばらす』の意味とは?
「ばらす」とは、映画や動画において、作品中の人物や背景、物語展開などを分解したり、その構造を明らかにしたりする行為を指します。この用語は、映画や動画の分析や批評の際に使用されます。たとえば、キャラクターの心理状態を「ばらす」ことで、その動機や行動の根拠を理解することができます。また、シーンの構成を「ばらす」ことで、監督の演出意図や物語の流れを把握することができます。 -

ばらしとは?映画や動画の用語解説
「バラシ」とは、映画や動画制作用語で、撮影された素材を時間軸に沿って並べることを指します。撮影された映像は、通常は多くのシーンに分割され、バラバラに記録されます。編集者はこれらのシーンを、ストーリーやテーマに沿って適切な順序に並べ直します。このプロセスを「バラシ」と呼び、編集作業の最初の重要なステップとなります。 -

映画用語『はめごろし』徹底解説
-はめごろしとは何か?- 「はめごろし」とは、映画用語で、登場人物が極限状態に追い込まれ、絶望的な精神状態に陥ることを指します。身体的拷問や心理的苦痛、社会的な孤立など、さまざまな要因によって引き起こされます。はめごろしのキャラクターは、理性と狂気の境界をさまよい、自身のアイデンティティや周囲の世界に対する感覚を失っていきます。彼らは、自暴自棄になり、絶望に陥り、最終的には破滅的な結末を迎える場合もあります。この用語は、ホラー、サスペンス、スリラーなどのジャンルでよく使用され、キャラクターの心理状態を強烈に描き出し、観客に強い印象を残す技法として用いられています。 -

映画や動画の用語「はける」を徹底解説
映画や動画の世界では、「はける」という用語を耳にすることがあります。この用語は、ある特定のシチュエーションや動作を表す際に使用されます。 「はける」とは、撮影シーンから姿を消すことを指します。舞台用語で「はける」という言葉が使われていたことに由来し、映画や動画でも同じ意味で使われるようになりました。つまり、俳優がカメラのフレームから姿を消し、シーンから退出することを意味します。 -

映画と動画の用語『はかま(二重を組み上げる脚のこと。)』
-はかまの意味とは- 映画や動画用語で「はかま」とは、二重に組んだ脚の動きを指します。一般的には、アニメーションでキャラクターが走る、跳ねる、回転するなどのアクションシーンで用いられます。「はかま」という名称は、股を広げて立つ相撲取りの土俵入りの動作に似ていることから名づけられました。 「はかま」は、キャラクターの動きに滑らかさとダイナミズムを与えるために使用されます。脚を二重に組むことで、勢いや躍動感が強調され、よりリアルで印象的なアクションシーンが表現できます。また、「はかま」はキャラクターの感情や意図を伝えるのにも役立ちます。例えば、大きな「はかま」は興奮や驚きを表し、小さな「はかま」は落ち着いた動きや忍耐を表します。 -

ハリモノとは?映画・動画用語を解説
ハリモノとは?映画や動画制作において、「ハリモノ」とは、現実的な背景や小道具を作成するために使用される、一時的な構造物やオブジェクトを指します。ハリモノは、現実的な場所を作成したり、既存の場所を拡張したり、特定のシーンやショットに必要な特定の要素を追加したりするために使用されます。 ハリモノは、さまざまな素材や技術を使用して作成され、その目的や予算に応じて、シンプルなものから複雑なものまであります。たとえば、実写の街並みを再現する大規模なハリモノから、机の上に置かれる小さな小物まで、幅広く使用されています。ハリモノは、撮影中に現実的な環境をを作り出し、観客の没入感を高める重要なツールです。 -

映画と動画における「張り出し舞台」とは?
張り出し舞台とは、舞台の端に突き出した、観客からよく見える小さな舞台のことです。この舞台は、通常、劇の中で重要な場面や独白が行われるために使用されます。張り出し舞台は、観客と俳優との間の親密さを高め、感情表現に重点を置くことができます。 -

張り手型とは?映画や動画における衝撃的導入部の活用法
張り手型とは、映画や動画の導入で衝撃的なシーンや情報によって観客の注意を引きつける手法です。この手法は、まるで視聴者の顔に張り手をくらわせたような強いインパクトを与えることから名付けられました。 張り手型の由来は、日本のテレビドラマや映画に見ることができます。日本の時代劇では、主人公が敵に対して張り手をくらわせ、観客に強い印象を与える手法がしばしば用いられました。その後、この表現力豊かな手法は他のジャンルの映画や動画にも取り入れられ、衝撃的かつ印象的な導入部を作成するために活用されるようになりました。